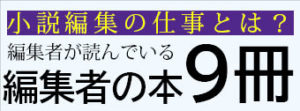自分の信じる面白さに正直でいること。それは決して悪いことでありません。たとえば、いかにもライトノベル的ではないライトノベルほど面白いという気持ち。誰も見たことがない斬新なストーリーは、きっとそういうところから生まれてきます。
一方でライトノベルにはカテゴリーエラーという考え方もあります。面白ければなんでもありとも言われるライトノベルであっても、あまりにもライトノベル的ではなさすぎるせいでカテゴライズできないもの。そういうカテゴリーエラーの作品は、新人賞であれば受賞する確率は下がりますし、書籍として出すのなら盛大にずっこけて惨憺たる売上げを記録する覚悟が必要です。
にもかかわらず!世界のどこかでカテゴリーエラーは作られ続けます。誰にも望まれていなくても、カテゴリーエラーは今日も、明日も、あさっても、ずっと生まれ続けていきます。それはいったいどうしてなのでしょう?
今日はそうした規格外の作品についての話題です。ライトノベルとカテゴリーエラーについてのお話をします。
ライトノベルをカテゴリーエラーにしたくない気持ちと、いかにもライトノベル然としたライトノベルにすることへの忌避感。正反対のようでいて、作家さんなら誰しもがもつであろう複雑な気持ちを編集者の視点からメモしてみます。
目次
「さて、何を書いたらいいですか?」
ライトノベルを書きたいのか。それとも小説を書きたいのか。
これは意外とむずかしい問題です。そもそも自分が書こうとしているものは何なのか。なんの疑いもなくライトノベルを書きたいと言えるならそれでOKなのですが、ライトノベルっていざ書こうとすると意外と書けないものですよね。
自分が書きたいものが一体なにかを把握することはプロでも難しいことなのです。
作家さんと打ち合わせをしていると「次は何を書いたらいいですか?」とか「さて、何を書きましょうか?」とたずねられることがあります。これには二つ理由があって、一つは「どんなお題でも出してほしい。期待を超える作品を書ける自信がある」というような、柔軟な企画屋タイプの気持ちからきているケース。特定の何かをテーマにして書きたいという気持ちよりも、読み手(ここでは編集者ですね)が求めるものを書く職業的な態度です。読み手ありきなサービス精神が先に立っているということです。
なんでも書けて、なにを書いてもプロの仕上がりの作品をきっちりと書く。そうして編集者の期待する以上の面白さで読者の予想を上回る素晴らしさを提供する。これはなかなかできることではありません。そうした仕事に自負と責任がある。だから書きたいかどうかなんて二の次でいい。書けるものを書けるように最高な状態で書いてみせる。そういう考えはたしかにあります。私はそういう職人的な作家さんを尊敬しますし、そういう方とのお仕事は発見が多く楽しいものです。
「マジで何書いたらいいんですか?」
そしてもう一つが、本当に自分が何を書きたいのかが分からないケースです。作家さんが書きたいものが見つからない。そのことに苦しんでいる。これは編集者にとっても頭の痛い問題です。プロの作家さんといっても、いつもいつでも創作のネタにあふれているということはなくて、ネタ切れをおこすことは当然あります。それでもインプットを続け、書きたい気持ちを湧きおこすために取材をがんばるという方もたくさんいます。それでも、やっぱり、書きたいネタが逆立ちしても見えてこないという事態は起こるものです。
企画書をいくつもいくつも編集者にボツにされて、書きたいものを目指すほどに理解されずに苦しい思いをする。そういう苦い経験の結果、自分の信じる面白さを見失ってしまったという作家さんもいるかもしれません。
もういっそライトノベルはやめてしまおうか。一般文芸の方向性をめざそうと思ったり、エキセントリックなネタで起死回生をはかろうとしたり。誰もやったことがないような反則スレスレの題材でやってやるか。需要を無視してオリジナリティで勝負だ。などなど。方法はそれぞれですがライトノベルからすこし距離をおき、ライトノベル的ではないものを書いてみたいという気持ちがムラムラわいてくる。迷いながら書き始めて、突っ走ったまま書き上げたもの……迷走した小説。それは、だいたいカテゴリーエラーになっちゃいます。
ライトノベル的ではないライトノベル
ライトノベルは面白ければなんでもありの総合格闘技みたいな小説のグループです。ラブコメで戦いを挑んでくるものもあれば、ファンタジーの王道ど真ん中をつきすすむものもあったり、メタな視点で風刺をきかせた面白さを見せつけるものだってある、まさにジャンルの坩堝と化しています。
ただ、SF作品や児童向けの娯楽小説、少女小説などの様々な源流をまぜこぜにして、スレイヤーズの登場というカルチャーショックを経た現在の「ライトノベル」は、なんでもありと標榜しつつも「お約束」や「不文律」みたいなものがゆるく存在していることも事実です。
たとえばボーイミーツガールであること。若い感性をもった読者の共感をよぶテーマをあつかっていること。ぜったいにこうでなければならない、というほどの強い制限はありませんが、ライトノベルというのはだいたい少年と少女がいて、若い読者が「分かる分かる!」とうなずきたくなるようなテーマを扱っているものです。
ということは、そうした要素を否定するだけであら不思議。ライトノベルレーベルから出版される立派なライトノベルでありながら、どうにもライトノベル的ではないライトノベルが誕生とあいなります。
ボーイミーツガールなし。おっさんばっかりでてきて、マイホームの話とか、税金の話とかばかりしているとか。いくら面白くても、それはライトノベルではないですよね。ライトノベルレーベルから出版されて、ライトノベルの棚に陳列されていれば見かけ上はライトノベルに見えるかもしれませんが、お約束を守る気ゼロではライトノベルにはなりません。
ライトノベルなんか書きたくない症候群
お約束をはずしたい。不文律をぶっ壊したい。
ルールの抜け穴を探したり、既存の枠にとらわれない奔放さは、時として創造に強烈なエネルギーを吹き込むものです。ライトノベルを避けて小説を書くことで、世間をあっと驚かせる傑作を生み出すことにつながる確信があるなら、それはもう誰にもとめることはできません。自分自身でも止められはしないでしょう。
またお約束をはずすことで手軽に目立つことができることも注目に値します。みんなが見慣れている絵も、上下逆さまにするととたんに見慣れない新作のように見えてしまうように、小説もありふれたお約束にちょっとアレンジをくわえることで労力以上の効果をあげることができると考えられます。
人と違うことがしたい。その願いは創作の原始的なエネルギーに他なりません。人と同じでよければ、そもそも作家を目指していませんよね。承認欲求なんて下品な言葉はあまり使いたくありませんが、作家さんは大なり小なり目立ちたがり屋の気があるものです。
人と違うことをするてっとりばやい方法といえばお約束をはずすこと。奇抜でニーズのない、ルール無用のカテゴリーエラー。これさえやっておけば、とりあえず手軽に目立つことはできてしまいます。目立ちたがり屋の気がちょっぴり満足するていどには。私はこれをこっそりと「ライトノベルなんか書きたくない症候群」と名前をつけて呼んでいます。
ライトノベルを書きたくないのは誰か?
書けないではなく、書きたくない。書けるけど、書きたくない。なぜならライトノベルなんか書いたら、自分のアイデンティティが傷つくから。かっこわるい、ダサい、オタクくさい、マイナスイメージのべったりついた軽薄でありふれたライトノベルなんか、自分のプライドが認めないから書きたくない。
「俺は本当はライトノベルなんか書きたくない」の似た仲間として「ライトノベル界に欠けている本物の文学性を追究したい」みたいなことを仰るケースもあります。ダサいのはいやだけど、ダサくなければ書きたい。かっこよくて、おしゃれで、オタクくささがなくて、高尚なイメージをかもしている斬新なライトノベルを書きたい。
ライトノベルをカテゴリーエラーにしているのは、実は作家さんではありません。作家には、作家としてのアイデンティティ(自己意識)と、その人自身の本名でのアイデンティティが境目なく混じりあっています。分かちがたくまざりあう公私のアイデンティティのうち、本名の領分が肥大してしまうとこのライトノベルなんか書きたくない症候群は発症しやすいようです。
自己意識を飼い慣らすのも才能のうち
カテゴリーエラーを意識した結果、ライトノベルを書けなくなってしまった場合には、まず自己意識に目をむけてみることをおすすめします。
ひとりの作家のなかにある、ふたつの自分。作家の看板を背負っている「自分」と、執筆から離れた個人としての「自分」。そう単純に切り分けることはできないふたつの「自分」のうち、果たしてどちらが「書きたくない」と思っているのか。あるいはどちらが「書きたい」と持っているネタなのか。それを冷静に観察してみたとき、作家としての自分の声を尊重する。すると、個人の私が一歩うしろにさがるはずです。
これはこの記事の最初のほうとも関連しています。「何を書きましょう?」と職業的に執筆にのぞむのは作家としての自分に重きをおいているわけですね。反対に「何を書いたらいいか分かりません」という場合は、個人としての自分の感性を企画の成否に組み込んでいるタイプといえます。
結局は、小説は作家に書かせるにかぎるということです。作家のなかにいる作家的な自分に書かせれば万事OK。個人の自分は、執筆する役ではというより、読んで楽しむファンの立ち位置がのぞましいでしょう。大切なのは自己意識に公私の区別をつけること。そして公(作家)の自分を尊重し、私(個人)の自己意識をうまく飼い慣らすことです。カテゴリーエラーな作品を面白いと思うのは自由ですが、それは個人の自分にまかせて。デビューを目指したり、新作の企画を前進させるたいなら、自己意識を冷静に見つめてみることがきっと役に立つはずです。